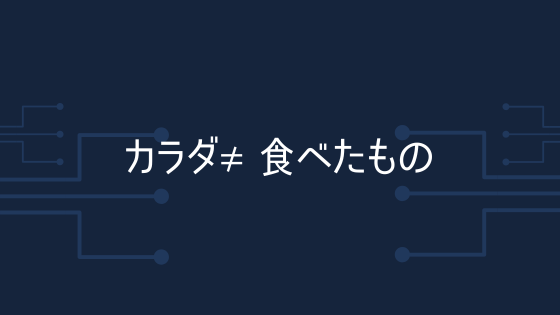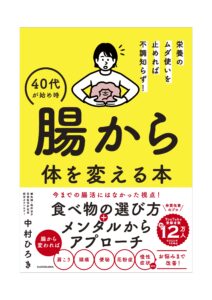「カラダは食べたものでできている」
このフレーズ、栄養学などを勉強すると必ず耳にしますよね。
でも、がんばって食物繊維や発酵食品をモリモリ食べてもぜんぜん調子が上がらない方々をみてきて、このフレーズには重大な落とし穴があることに気づきました。
===
私たちが食材を「食べる」という行為は、実は体づくりの最初のステップに過ぎません。食べたものが真に栄養となるには、消化、吸収、そして細胞へ運ぶという長い長い道のりを滞りなく進まなければいけません。
まずは消化の段階。タンパク質はおもに胃で消化されます。糖質は口の中から消化が始まります。しかし、ストレスで胃が動いてなかったり、咀嚼不足で唾液が出ていなかったりすると、消化不良が起こります。消化しきれなかった食材は、せっかく摂取しても栄養として使われずに排出されてしまいます。
次に吸収の段階。腸まで達したドロドロの内容物が、腸の壁をすり抜けて血管内に入ることを「吸収」といいます。そして血管から栄養を必要としている細胞まで運ばれて、はじめて食材から摂取した栄養は「カラダの一部」となるのです。
ここで重要なのは、吸収機能もメンタル状態に大きく左右されるということ。怒っている人の胃を調べた研究では、肉の消化時間が通常の2倍もかかったというデータもあります。ストレスや感情が、どれほど内臓のはたらきに影響するか痛感しますね。
===
一般的な栄養学は「何を食べるか」「何を避けるか」という食材選択の話に終始しがちです。でも、摂取行為は食事の一部に過ぎません。食事には、食材以外にも大切な要素がたくさんあります。
例えば、穏やかな気分で食べること、好きな人と楽しく食べること、美味しいと感じながら食べることなど。実際に、胃もたれで長年悩んでいた方が、大好きな友人と大好きなものを楽しく食べるようにしただけで、症状が大幅に改善した事例もあります。
飲食店で店員さんが怒られている場面に遭遇してしまい、ゲンナリした経験ないですか?これは単なる気分の問題ではなく、その瞬間に交感神経が優位になり、胃腸機能が実際に低下しているのです。つまり、食べる環境や雰囲気は、消化機能に直接的な影響を与えているのです。
===
それからもう一つ。
栄養は収支で考えることが大切です。良質な食材を摂取し、それを消化吸収できたとしても、その栄養がムダ遣いされていては意味がありません。
寝不足やストレスがあると、カラダを元に戻すために多くの栄養素が消費されます。寝る間を惜しんで健康情報を夜中まで収集して寝不足になれば、せっかく摂取した栄養がその疲労回復に使われてしまう。本末転倒です。
ここでいう「ストレス」とは、イライラだけではありません。
自分と違う人や考えを敵視してしまう状態、雑談できる相手がいない孤独感、過去の後悔や未来の不安で頭がいっぱいな状態なども含まれます。これらは常に交感神経を優位にし、大量の栄養を消費します。
===
結論として、正確には「カラダは余った栄養でできている」といえます。慢性症状を改善するためには、栄養を摂取だけでなく、消化吸収を妨げる要因を減らし、ムダな栄養消費を抑えることが重要です。
食材選びも大切ですが、それ以上に食べる環境や心理状態、生活習慣全体を見直すことが大事であること、おわかりいただけたでしょうか・・?