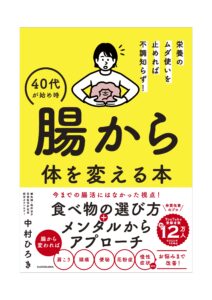「第6の栄養素」と呼ばれる食物繊維。多くの人が体に良いものと信じて疑いませんが、慢性症状を抱えている人には、必ずしもプラスに働くとは限りません。
食物繊維には不溶性食物繊維(ごぼう、さつまいもなど)と水溶性食物繊維(海藻類など)の2種類があります。それぞれ体内で良い作用をしてくれる側面がありますね。
しかし、そのチカラを発揮するまでには、いくつものハードルが存在するんです。
===
不溶性食物繊維が便のかさ増しという本来の役割を果たすためには、たとえば以下の条件が必要です。
・十分な咀嚼: 繊維を細かくしないと腸壁を傷つける可能性
・適切な水分摂取: 水分不足だと便が固くなってしまう
・腸の蠕動運動: 自律神経(特に副交感神経)の正常な働きが必要
つまり、せっかく玄米を食べていても、早食いをしていたり、水分不足だったり、ストレスで交感神経優位になっていると、逆に便秘が悪化する可能性があるのです。
水溶性食物繊維も同じです。
善玉菌のエサになったり便を柔らかくしたりする前に:
・咀嚼が必要: 血糖値や脂質の吸収を緩やかにする作用を発揮するため
・IBSやSIBOがないこと: 過敏性腸症候群や小腸内細菌異常増殖症があると、小腸でガスが発生し腹痛の原因に
食物繊維を味方にするため、いかに大前提として満たすべき条件があるかおわかりいただけるでしょう。
===
では、食物繊維を味方にする3つのポイントを解説します。
1. 答えはカラダの中にある
外側の情報(YouTubeやネット)に正解を求めるのではなく、実際に食べた時の自分の体の反応を観察することが最も重要です。
高FODMAP食材でもお腹が張らないものもあれば、低FODMAP食材でも合わないものがあります。
2.「体質改善食」を理解する
以下の2種類の食事は、なんとなく皆さんイメージできると思います。
・病院食: 入院患者向けの消化に負担の少ない食事(おかゆなど)
・健康食: 健康な人向けの栄養価重視の食事(玄米やプロテインなど)
でも、個人的にこの2つの間には大きな開きがあると思っています。そこで重要になるのが「体質改善食」です。
ぼくがつくった概念なのでググっても出てこないと思いますが・・
体質改善食とは、慢性症状(便秘、腹部膨満、疲労感など)で長年悩んでいる人が摂るべき食事のこと。
病院食ほど制限的ではないが、健康食ほど負荷をかけない中間的な食事法を指します。
例えば:
・玄米ではなく白米から少ない消化負担でエネルギーを摂る
・大量のプロテインではなくアミノ酸からタンパク質補給をする
・食物繊維や発酵食品はお腹に変調があるなら積極的に摂らない
多くの人が「健康に良い」とされる健康食を摂っているのに体調が改善しない理由は、実は体質改善食を摂るべき状態だからかもしれません。
慢性症状がある時は、自律神経の乱れなどで消化吸収能力が低下しているため、健康な人が普通に消化できるものでも負担になってしまうのです。
3. 便秘にはマグネシウムを優先
便秘のひとこそ食物繊維を摂りたがるのですが、ここまでお話ししたように食物繊維ってけっこうハードルが高いです。個人的に、便秘に対して優先すべきは圧倒的にマグネシウム>食物繊維です。
食物繊維のように消化負荷がないだけでなく、ストレスや過労で大量消費されるマグネシウムは、慢性症状でお悩みの方の大半が不足しているからです。
(それでいて腸内に水分を集める働きで便秘に有利な作用がある)
===
栄養素には優先順位があります。
C(炭水化物)→ P(タンパク質)→ O(その他)の順で問題解決することが大切です。食物繊維はここでいう「その他」なんですね。
低血糖や低タンパクなど、それより上位の問題があるなら、ここから解決するほうが失敗が少ないですよ。
※本記事の内容は以下のYouTube動画を要約したもの