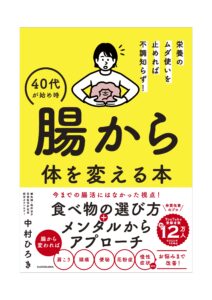体質改善に取り組んでも症状が「あと一歩」のところで改善が止まってしまう。その原因の多くは、体内で「炎症が止まらない」ことにあります。
「炎症は悪いもの」という認識は誤解です。炎症は体に異常が起こった際の「修理反応」であり、生命維持に欠かせません。問題となるのは、必要のない場所で慢性的に起こる「無駄な炎症」です。
炎症の程度は血液検査で推測できます。
CRPは0.03以下が正常ですが、0.05~0.07といった「地味に高い」状態は体内の炎症を示します。白血球数も重要で、基準値5,000に対し7,000~8,000なら腸内炎症、10,000超はアトピーなど強い炎症の可能性があります。
===
以下、炎症と関連する栄養素をまとめました。
1. オメガ6とオメガ3のバランス
オメガ6(=炎症促進)とオメガ3(=炎症抑制)の理想比率は4対1ですが、現代人は10対1になっています。揚げ物や外食でオメガ6過多になりがちなので、青魚やナッツでオメガ3を意識的に摂取しましょう。
2. マグネシウム
研究では、マグネシウム不足者のCRP値が1.5~1.8倍高いことが判明しています。筋肉をゆるめる働きがあるため、不足すると目のピクピク、偏頭痛、生理痛、こむら返り、便秘などが起こります。ストレスや飲酒で大量消費されるため注意が必要。
3. ビタミンB6
VB6不足者はCRP値が高く、関節リウマチになりやすいデータがあります。血液検査でALTがASTより2以上低い場合、B6不足を疑います。女性ホルモン、睡眠ホルモン、幸せホルモンの合成に必要で、不足すると婦人科系トラブル、睡眠障害、メンタル不安定の「トリプルパンチ」が起こります。
4. ビタミンC
強力な抗酸化作用で炎症を促進する活性酸素を無毒化します。血中濃度が高い人ほどCRP値が低いという明確なデータもあります。風邪をひきやすい、歯茎から出血、傷が治りにくいなどの症状が複数あれば不足の可能性。
5. ビタミンD
VD不足者には腸の炎症性疾患が多く見られます。血中25-OHビタミンDの理想値は50~70ng/mlですが、現代人の平均は約20ng/mlと深刻な不足状態です。花粉症や冬季うつの症状があれば不足を疑ってください。
===
多くの人は栄養摂取量ばかり気にしますが、慢性症状が治るのは体内に「余った栄養」によるものです。せっかく摂取した栄養がストレスなどで浪費されては意味がありません。栄養は収支でかんがえるのが大切です。
これが「心身一体」の考え方です。体質改善は栄養とメンタルの両輪で進める必要があり、栄養摂取と同時にストレス管理も重要になります。
まずは血液検査でCRPと白血球数をチェックし、5つの栄養素の不足症状を確認してください。最も不足している栄養素から優先的に補給を開始し、同時にストレス対策も行いましょう。
炎症は決して悪者ではありませんが、慢性的に続く不要な炎症は体質改善の大きな妨げとなります。これら5つの栄養素で体内の炎症バランスを整え、「あと一歩」の壁を突破してください。
(※このコラムは、YouTube配信をテキスト化したものです)